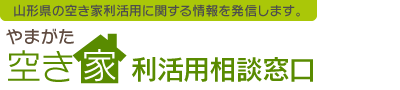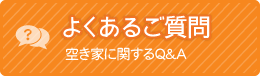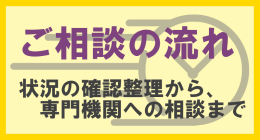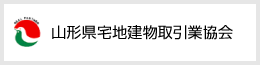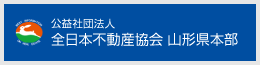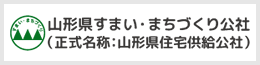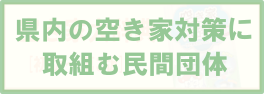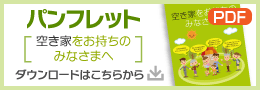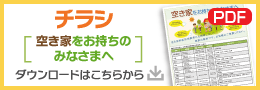お客様からお問い合わせの多いと考えられる質問をQ&Aとして掲載。
全般
 Q1.空き家を利活用(売買したい・賃貸したい等)したいが、具体的にどうしたらよいかわかりません
Q1.空き家を利活用(売買したい・賃貸したい等)したいが、具体的にどうしたらよいかわかりません- A1.空き家の利活用をご検討の方は、空き家利活用相談窓口にご相談ください。
―空き家利活用相談窓口はこちら― - Q2.空き家を『どうしたらよいか』、『どこに相談したらよいか』わかりません
- A2.総合案内窓口にご相談ください。
状況をお聞きして、賃貸や売買、管理、解体等の選択肢をアドバイスのうえ、相談先をご案内します。
総合案内窓口
電話窓口 023-679-5255
(山形県すまい・まちづくり公社 まちづくり推進課内)
開設日・時間 毎月第2・4火曜日
10:00~12:00、13:00~16:00
祝日など休業日を除く - Q3.相談は無料ですか?
- A3.窓口での相談は無料です。
ご相談の内容によって専門団体等の相談先をご案内することがありますが、専門団体等でのご相談については有料のものもあります。
◎『相談窓口』ページはこちら - Q4.住む予定のない家を相続したが、空き家を放置するとどうなるか?
- A4.空き家は、通常の家屋より速いスピードで老朽化が進むため倒壊の恐れがあり、通行人や近隣に人的被害を招きかねないこと、植込みの成長によって近隣迷惑となること、不法侵入など犯罪の誘発に繋がる等の問題が発生するなどの可能性があります。使う予定がない場合は、賃貸や売却なども検討されることをお勧めします。
また、令和6年4月から不動産の相続登記が義務化されました。登記をしない場合、過料の対象となる場合があります。 - Q5.空き家を活用する場合と取り壊した場合に、税は変わるか?

- A5.建物が「居宅」の場合、土地の固定資産税の軽減措置を受けることができますが、取り壊して更地にすることで軽減措置が受けられなくなります。
なお、空き家を取り壊さず、空き家等対策の促進に関する法律による「管理不全空家等」「特定空家等」として同法律による除却等の措置勧告を受けた場合、土地の固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。 - Q6.空き家があるが相続するかどうか、税金のことなどを専門家に相談したい。
- A6.専門家による相談窓口をご紹介します。
◎『事業者リスト』ページはこちら
貸したい場合・売りたい場合
- Q1.空き家を売却(賃貸)したい。どのようなことを考えればよいか。

- A1.空き家を売却(賃貸)する方法については、空き家の所在地に詳しい不動産業者に依頼する、もしくは行政の「空き家バンク」に登録することが考えられます。
不動産業者に依頼、または「空き家バンク」に登録するために、土地・建物の状況(登記上の所有者、面積・形状、接道状況、建築年、増改築・修繕履歴、管理の状態)や周辺環境などを整理しておく必要があります。情報の整理については、空き家相談シート(相談者用)を参考にしてください。
建物の状況を知るためには、住宅診断(ホームインスペクション)や耐震診断を行うことも考えられます。
◎相談シート(相談者用)
空き家所在地域の不動産業者に関する相談先は当協議会ホームページの『空き家相談窓口』ページ、空き家バンクについては『空き家の情報』ページをご覧ください。 - ◎『空き家の相談窓口』ページ
- ◎『空き家の情報』ページ
- Q2.空き家を売りたい(貸したい)がいくらで売れる(貸せる)か見当がつかないが、どうしたらよいか?
- A2.土地・建物の状況(上記Q1を参照)や周辺環境などによって異なるため、空き家所在地に詳しい不動産業者への相談をおすすめします。空き家所在地域の不動産業者に関する相談先は、当協会ホームページの『空き家相談窓口』ページをご覧ください。
また、専門家(不動産鑑定士)に調査を依頼する方法があります。
なお、最終的には売主(貸主)の判断で希望売買価格(賃料)を決定するケースが多いようです。
◎『空き家の相談窓口』ページ - ◎『事業者リスト』ページ
- Q3.リフォームしないと売ったり貸したりすることはできないか?
- A3.賃貸の場合、建物の構造にかかる箇所や付属する電気設備・給排水設備などは所有者負担で修繕し貸す以外に、入居者がリフォームを行う『DIY型賃貸借』という方法があります。
売買の場合でも、修繕せず、そのまま取引するケースもあります。
自治体によってはリフォーム補助金制度がある場合がありますので、確認してみてください。
◎県ホームページ『タテッカーナ』(支援情報をご覧ください。) - Q4.空き家をリフォームしたい場合、どこに依頼すればよいか?
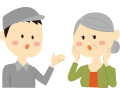
- A4.建設、建築および設計に関する専門家の協会をご紹介します。
◎『事業者リスト』ページ - Q5.賃貸に出したいが家財が残っている。どうすればよいか?
- A5.空き家に残っている家財等については、借り手としては不要となることが多いため、空き家所有者が処分をすることになります。
遠方にお住まいの場合など、ご自身で処分することが難しい場合は、業者に委託する方法をご検討ください。
また、処分しない場合はトランクルーム等に預ける方法もあります。
借りたい場合・買いたい場合
- Q1.空き家情報はどこで見られるか?
- A1.各不動産業者のホームページや、自治体が「空き家バンク」を立ち上げ、インターネットで情報を公開しているケースがあります。空き家バンクについては、当協議会ホームページの『空き家の情報』ページや山形県のホームページをご確認ください。
- ◎『空き家の情報』ページ
◎県ホームページ『すまいる山形暮らし情報館』 - Q2.空き家物件を紹介してほしい。

- A2.ご希望の地域に詳しい不動産業者に問い合わせるか、もしくは行政の「空き家バンク」に登録されているかご確認ください。
お問合せ先については、地域の不動産業者は当協議会ホームページの『空き家相談窓口』ページ、空き家バンクについては『空き家の情報』ページをご確認ください。
◎『空き家相談窓口』ページ
◎『空き家の情報』ページ - Q3.不動産業者への仲介手数料は発生するか?
- A3.不動産業者の仲介により成約した場合、原則として仲介手数料が発生します。
なお、トラブルを未然に防止し円滑な取引を行うためにも、専門家である不動産業者に仲介を依頼することが望ましいと考えられます。 - Q4.賃貸の場合、空き家を自分たちで改造してもよいか?
- A4.日常の維持管理などを超える大規模な修繕(屋根・外壁など)や改造(間取り変更など)については、貸主と締結する賃貸借契約の内容に従うことになります。貸主の承諾を得ずに建物の改造等を行った場合には、賃貸借契約を解除されることもあり得ます。後々トラブルにならないよう、どこまで改造等が可能かどうか事前の確認が必要です。
空き家を適正に管理したい場合
- Q1.相続した空き家がある。いずれは住みたいが他人に貸すつもりはない。どうしたらよいか?
- A1.人が住んでいない家は速いスピードで老朽化が進むため倒壊の恐れがあり、通行人や近隣に人的被害を招きかねないこと、植込みの成長によって近隣迷惑となること、不法投棄の温床など犯罪の誘発に繋がる等の問題が発生するなどの可能性があります。
このことが原因で火災や事故が発生して他人に被害を与えた場合は空き家所有者の責任になりますので建物の定期的な管理が必要です。
ご自身での管理が困難な場合は、業者に空き家管理を依頼する方法があります。 - Q2.空き家管理とは、具体的にどのようなものか?
- A2.定期的に建物の状況、敷地の状況について確認を行い、問題が確認できた場合や周辺住民等から苦情等のトラブルがあった場合に問題・苦情に対応することです。
具体的には、建物の換気、清掃、草取り、雪下ろし等の手配、郵便ポストの整理、外周の清掃、室内の簡易清掃、目視で可能な範囲での屋根・外壁・塀の点検等です。
確認等を業者に依頼する場合には、料金のほか、実施内容、頻度等を確認すると良いでしょう。
また、維持管理という点では、固定資産税などの支払い、水道料金基本料金など公共料金の支払いや火災や自然災害に備える保険料の支払いなども考えられます。 - Q3.空き家を寄付、無償譲渡したいが、どこに相談すればよいか?
- A3.自治体の中には土地・建物の寄付を受け付けているところもありますので、詳しくは各自治体にご相談ください。
その他、空き家バンクを利用して無償による譲受希望者を探したり、民間による空き家の無償譲渡取次ぎサービスを利用する方法も考えられます。
なお、無償譲渡の取引では不動産業者が介入できないこと、譲渡人には譲渡所得税、譲受人には贈与税や不動産取得税等の費用が発生する場合があることに注意しなければなりません。
空き家を解体したい場合
- Q1.空き家が倒壊の危険があるので解体したい。どこに依頼すればよいか?
- A1.解体に関する専門の協会を紹介しますので、具体的な工事内容・見積もり等の相談は相談者が直接お問い合わせください。
◎『事業者リスト』ページ - Q2.老朽化した住宅を解体したいが、費用はどれくらいかかるのか?
- A2.解体費用は住宅の規模・構造によって変わってきますが、目安として下記をご参考ください。ただし、建物が小さい場合、建物まで重機が入れない場合等は割高になる場合があります。
■木造住宅3〜5万円/坪程度 ■鉄骨造3〜5万円/坪程度 ■RC造4〜6万円/坪程度
また、上記以外に養生費用、アスベスト材の処分費用、不要家財(生活ごみ・廃棄家電等)の処分費用、樹木の伐採・処分費用などがかかる場合があります。 - Q3.解体したいが資金がない。どこに相談すればよいか?
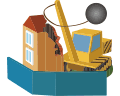
- A3.自治体の中には廃屋状態になっている空き家の解体費用を助成しているところがあります。
詳しくは各自治体へお問い合わせください。
◎県ホームページ『タテッカーナ』(支援情報をご覧ください。)
相続・その他
- Q1.建物を管理する人がいない場合はどうなるのか?
- A4.所有者が死亡し相続人がいない、もしくは相続人が全員相続放棄してしまうと建物を管理する人がいなくなるため、民法の規定によって相続財産法人となり、管理するためには管理人を選定する必要があります。
通常は利害関係者が裁判所に選任の申し立てを行いますが、誰も申し立てを行わない場合は検察官が申し立てを行います。
管理人が選定されれば管理人がその後の管理を行います。 - Q2.空き家の所有者が認知症なのだが、空き家の処分を身内でできるか?
 A5.まずは成年後見制度の利用をお勧めします。成年後見の申し立ては、本人・配偶者4親等内の親族ならできます。
A5.まずは成年後見制度の利用をお勧めします。成年後見の申し立ては、本人・配偶者4親等内の親族ならできます。
成年後見人は裁判所が選任しますが、実態としては司法書士が選ばれるケースが多く、弁護士・親族・社会福祉士が続くようです。
相談窓口としては家庭裁判所の他に、専門家として司法書士、弁護士、行政書士などが考えられますので、専門家の協会をご案内いたします。
◎『事業者リスト』ページ
空き家のことで迷惑を被っている場合
- Q1.空き家の苦情や相談はどこにすればよいか?
- A1.老朽化した危険な空き家等についての苦情や相談は、各自治体の担当課へご相談ください。
一般的に、防火・防犯等の安全性に関連すること、建物の倒壊等の建物指導に関すること、ごみの不法投棄・雑草の繁茂等の環境衛生に関することで担当課が異なる場合があります。
なお、空き家が原因で実害を受けている等の場合には、弁護士などの専門家に相談することも考えられます。
◎『事業者リスト』ページ - Q2.空き家になっている隣家の木が越境していて何とかしたいが、所有者が不明なときはどうすればよいか?
 A2.法務局へ行って登記事項を閲覧すれば所有者がわかるので、所有者に対して越境している部分は切ってくれるようお願いすることができます。
A2.法務局へ行って登記事項を閲覧すれば所有者がわかるので、所有者に対して越境している部分は切ってくれるようお願いすることができます。
令和5年4月から、越境している枝の切除を催告したが相当の期間に切除しない場合、所有者またはその所在を知ることができない場合、急迫の上場があるときには、越境している枝を自ら切り取ることができるようになりました。この手続きについては、弁護士など専門家に相談して行うことが良いと考えます。
◎『事業者リスト』ページ